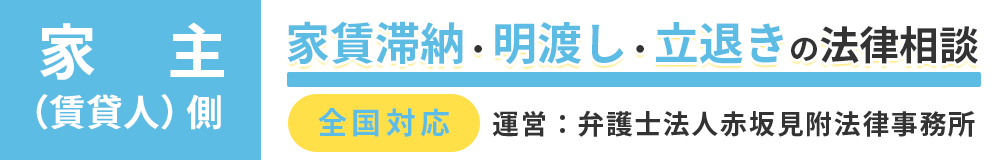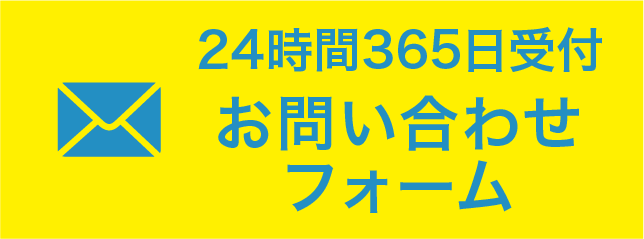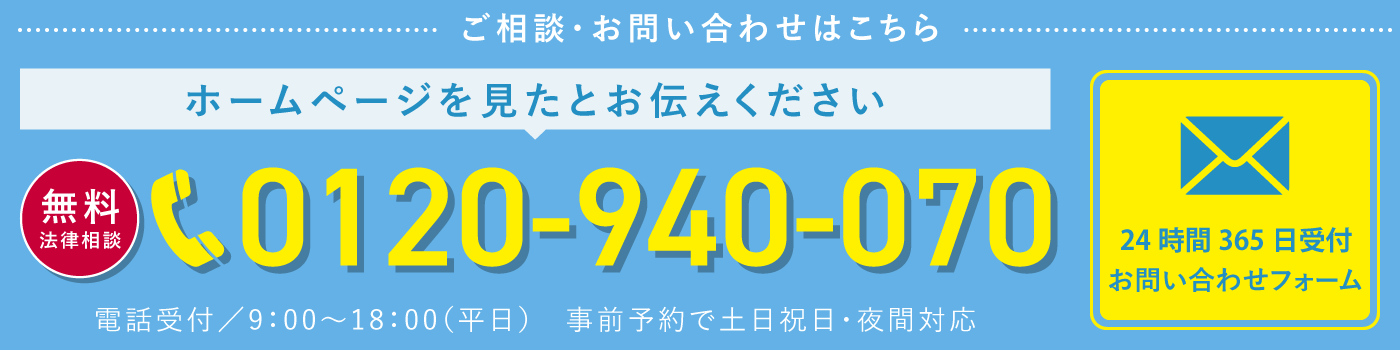契約
自力救済の禁止
裁判による権利の実現
建物の明渡しや、金銭の支払いなど、契約や法律により、相手に対して何らかの請求ができる場合があります。
しかし、相手が任意に明渡しや支払いをしない場合は、これを強制的に(相手の意に反して)実現する必要があります。
日本の法律上、そうした権利を実現するためには、裁判所の手続を要することになっています。
すなわち、権利者は、①請求する権利があることを裁判所に認めてもらった上で、②その権利を裁判所の執行官等の力で実現する手続を取る必要があります。
自力救済とは
自力救済とは、裁判所の手続によらずに、自ら権利を実現する行為をいいます。
すなわち、明渡しや支払いなどの権利につき、契約や法令上の根拠はあるものの、上記の①や②の手続を経ずに権利を実現することを指します。
建物の賃貸借契約において問題となるのは、家賃滞納の事実やそれを理由とした解除の事実があった場合、あるいはそれらを認める判決があった場合に、明渡しを自ら実現する(不在中に鍵を交換したり、荷物を搬出したりする)ことです。
建物明渡における自力救済の問題
近時、不動産業者や家賃保証会社の中に、正当な手続を経ずに、違法な「追い出し行為」により明渡しを実現する会社があり、問題となっています。
追い出し行為としては、不在中の鍵の交換、大声や威圧するような督促、深夜や早朝、高頻度の訪問などです。こうした行為は、慰謝料等の損害賠償の対象となるほか、恐喝、暴行等の刑事罰の対象となる可能性があり、結果的に紛争の早期解決が困難となります。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。
賃貸借契約の更新
更新とは
賃貸借契約の更新とは、期間が満了した際に、同等の契約関係を継続することです。
契約には、売買契約や請負契約など、一回で終わる形の契約と、賃貸借契約や業務委託契約など、関係が継続する形の契約があります。
後者の継続する形の契約は、定められた期間が満了しても、同等の関係を継続することを当事者が望む場合もあり、そうした場合は契約を更新することになります。
更新には、合意更新・自動更新・法定更新などの種類があります。
合意更新
合意更新とは、双方が更新することを合意してなされるもので、最も一般的です。
賃貸借契約の期間満了のたびに、更新契約書に署名捺印をするのが、合意更新です。
内容は従前と同条件とすることが多く、期間の長さも同様とすることが多いです。ただし、双方の合意によるものですので、内容を変更することも可能です。家賃の減額であったり、利用条件の変更であったり、双方で合意に至れば、契約の規定は自由に変更できます。
自動更新
契約書の中に「双方から反対の意思が表示されない場合は、同じ条件で更新するものとみなす」というような条項が入っている場合があります。これは広い意味では、合意による更新の一種ですが、何もしなくても更新されるという点では後述の法定更新と似ています。
法定更新との違いは、更新後の契約にも期間が定められることです。自動更新と法定更新とを比較した場合に自動更新が借家人に不利益とはいえないので、自動更新条項も有効とされています。
法定更新
法定更新とは、当事者の更新の合意はないけれども、法律上更新されるというものです。
建物の賃貸借契約で、何もせずに契約期間が満了した場合でも、契約は継続します。自動更新条項がなくてもです。これを法定更新といいます。
法定更新では、ほとんど全ての契約条件が引き継がれますが、契約期間のみは引き継がれません。期間の定めのない契約になってしまうのです(借地借家法26条1項ただし書)。
期間の定めがないと聞くと、一般の方の中には「ずっと契約が続く」と肯定的に捉える方がいるかもしれませんが、そうではありません。期間の定めがないと、家主からはいつでも解約の申入れができるため、期間の定めがある場合に比べて、家主から契約終了をさせる機会が増えます。
法定更新をしないための手続
何もしないと法定更新となってしまうため、家主が期間満了と共に契約を終了させたい場合は、積極的に手続を取る必要があります。
必要な手続は2つです。一つは、期間満了の半年前までに更新しないとの通知を行うこと。もう一つは期間満了後に相手がまだ利用していた場合、速やかに異議を述べること、です(借地借家法26条1項・2項)。
このように手続を取ったうえで、かつ更新拒絶のための正当な事由が必要です(借地借家法28条)。
手続においても理由においても、家主に求められる水準は高く、見方を変えれば、借家人が非常に手厚く、建物の利用継続の権利を保障されている、ということができます。
更新料
更新の際に更新料の支払をすべき、とする契約は一般的です。首都圏では家賃1ヶ月分の更新料という定め方が多いように思います。
更新料の定め自体は有効とされています。
なお、合意更新や自動更新の際に、更新料の支払義務を規定していたとしても、法定更新の際にも更新料の支払義務が肯定できるとは限りません。
契約書の記載にもよりますが、裁判例によっては、法定更新の場合には更新料の支払義務はないとしたものもあります。
さらにいえば、法定更新となった場合、その後は期間の定めがなくなります。そうすると、更新自体がなくなるため、理屈としては、当初の法定更新のときはともかく、その後の更新時期の更新料の支払義務がなくなると考えることができます。
借家人の中には、そうした解釈ができることをいいことに、ある時点から法定更新となったと主張してその後の更新料の支払を拒む者がいます。
これに対しては、双方が契約の継続を企図している以上、更新の黙示の合意があったとして、合意更新を主張することもできるかもしれません。いずれにしても自動更新条項を入れておくのがよいと思われます。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。
定期建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約(定期借家、定借)とは
建物の賃貸借契約には、通常の建物賃貸借契約とは異なる、定期建物賃貸借契約という契約形態があります。「定期借家契約」と呼んだり、「定借(ていしゃく)」と呼んだりします。
これは、定められた期間が終わるときに更新がない契約のことです。名称こそ「定期」となっていますが、期間が定められているのは他の借家契約も同じで、むしろ「更新がない」点が重要です。
普通借家契約の継続性(更新)
普通の建物賃貸借契約(普通借家契約)にも、通常は期間が定められています。一般的な契約では2年間か3年間という長さが多いです。
しかし、2年間の契約だからといって、必ずしも2年後に部屋を明け渡さないといけない、というわけではありません。更新するかどうかは、借家人が自由に決められることが多いです。
これは法律上にも規定があり、普通の借家契約で家主が更新をしない(更新拒絶する)ためには、正当な事由(正当事由)が必要とされています(借地借家法28条)。しかも、「自分が住みたいから」など、理由があればなんでもよいわけではありません。具体的で重要な理由が必要な上、併せて一定額の立退料の支払も求められることが多いです。
裁判においても、入居者は保護され、家主には厳しい判断がなされる傾向にあります。
家主としては、普通の賃貸借契約の場合、借家人が自ら出ていくまで継続する、との認識を持っていた方がよいことになります。
定期借家契約の目的
普通の賃貸借契約では、借家人がいつ退去するか判りませんし、どうしても退去してもらいたいという場合には立退料や裁判などの金銭的、時間的な負担が大きくなります。
そこで、一定の期間の後に退去してもらう必要があると判っている場合(自己利用や、建替など)は、入居する際に、定期借家契約の形にすべきです。当初の契約期間が終了した場合に、相手に退去を強制することができます。
裁判所の借家人保護の姿勢などを目にする機会が多い弁護士としては、将来的な利用方法がはっきりしない場合でも、定期借家契約を結んでおくことがよいように思います。
さらにいえば、将来的な利用方法がはっきりしない場合でも、定期借家契約にしておくことで、選択肢を確保できます。したがって、「いつまででも長く住んでもらいたい」という場合でない限り、定期借家契約を積極的に活用することをお勧めします。
定期借家契約の手続、特徴
定期借家契約の締結には特別な手続が必要です。
まず、契約時の手続ですが、定期借家契約であることを契約書などの書面(必ずしも公正証書でなくてもよいです。)に明記した上で、さらに、「更新がないこと」「期間満了により終了すること」を記載した文書を、別途準備して相手に交付し、説明しなければならない、ということです(借地借家法38条)。
次に、終了時の手続ですが、期間満了の半年以上前(かつ1年前より後)に、契約が終了することを通知しておかないといけません。
このように定期借家契約の手続は特殊です。そしてこうした手続に不備があると、定期借家ではなく、普通借家とされてしまう場合があります。そこで、初めて定期借家契約を結ぶ場合や、自信がない場合は、弁護士などの法律の専門家に相談するか、経験の豊富な不動産仲介業者に書式等の準備をしてもらうことをお勧めします。
なお、定期借家の家賃は、通常より安く設定されます。入居者からすると、退去期限が自分の都合で延ばせないという点が普通借家契約に比べて不利なためです。期間にもよりますが、普通借家の相場に比べると、概ね1割から2割程度安い例が多いようです。
建物を貸す際には、是非、定期借家の活用を検討していただきたいと思います。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。
賃貸借契約の修繕義務
修繕義務は家主か借家人か
建物の賃貸借契約において、建物や付属設備が壊れた場合に、誰が修理・修繕の義務を負うでしょうか。細かいところでは、照明や水道、建具などの消耗品の劣化などもありますが、より大きなものとしては、エアコンやトイレ、電気系統なども壊れることがあります。さらには、天井からの雨漏りや、外壁・階段の破損、地盤沈下など、建物や敷地自体に問題が生じることもあります。
このように、ときに高額となりかねない修繕費用について、負担者をきちんと理解しておく必要があります。
原則として修繕は家主(オーナー)の責任
賃貸借契約は、借家人(賃借人)が家賃を払うことと、家主(賃貸人)が建物を使用させることが、対価的な関係にあります。ということは、家主は建物について、使用可能な状態にしておかなければならないのです。
したがって、建物側に不具合があって、使用に支障があるのであれば、その不具合を取り除く、つまり修繕する責任は家主にある、ということになります。
これが基本であり、民法上も「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と明文で規定されています(民法606条1項本文)。
破損が借家人による場合
原則として家主にある修繕義務ですが、破損が借家人の不適切な利用方法による場合は、当然のことですが、借家人が修繕すべきです(民法606条1項ただし書き)。
借家人が誤って壁を破損した場合や、過失により漏水事故を起こした場合、鍵を紛失して交換しなければならない場合などです。
借家人への修繕義務の転換
契約書の記載により、通常は家主が負うべき修繕義務を、借家人の負担とする事も可能です。
電球や電池の交換や水回りのパッキンの交換など、軽微な修繕については、借家人の負担としている契約書も多いです。
もっとも、仮に契約書に修繕義務を借家人の負担とする定めがあっても、大修繕については、特別の事情がない限りは借家人の負担とすることは困難と考えられます。
古い家を安い家賃で貸している場合などで、修繕義務を賃借人の負担としたい場合、後に争いとならないよう、その範囲と理由を書面で確認しておくのが望ましいでしょう。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。
賃貸借契約の違約条項
定型の契約書
賃貸借契約を結ぶ場合、多くは不動産業者の用意した契約書をそのまま利用すると思います。
あるいは、自ら準備する場合であっても、書店等で購入可能な定型の書式を利用することはあっても、自分で全部作成する方はほとんどいないでしょう。
定型の書式等での契約は、過不足なく記載があり安心ですが、必ずしも賃貸人に有利な条項ばかりではありません。内容もよく確認する必要があります。
賃貸人が是非とも入れたい違約条項
賃貸人として、入れておきたい違約条項は次の通りです。
- 賃料等の遅延損害金は年14.6%にする
- 契約終了後の明渡遅延については、賃料倍額の損害金とする
これらは、いずれも有効と考えられており、家賃滞納や契約違反、そして契約解除後の明渡しに際して、非常に効果的な条項です。
賃料等の遅延損害金は年14.6%
本来、特に利率を定めない場合、遅延損害金は民法の法定利率に従いますので、年3%となります。それでも昨今の低金利の世の中では高い方ですが、これを14.6%とすれば、相手に対するプレッシャーとなります。
なお、消費者契約法において、消費者が相手の場合は年14.6%を超える損害金の定めは、その超過部分が無効とされています(消費者契約法9条2項)。
入居者が消費者に当たらない場合(法人や団体、あるいは個人事業者)であれば、年14.6%を越える定めも有効ですが、少なくとも年14.6%に設定しておくのがよいでしょう。
なお、年利14.6%というのは、日歩4銭(1日当たり100円に対し0.04円→365日で14.6円)が由来のようです。
明渡遅延の場合は賃料倍額の損害金
賃貸借契約書のうち、約半数くらいの印象ですが、契約が終了した後に明け渡さない場合、ペナルティとして賃料の倍額の損害金を支払う義務がある、とする条項があります。
この条項は、賃貸借契約書の条項の中でも非常に重要な条項の一つです。
内容は簡単で、契約が終了しても明け渡さなければ、家賃の倍の支払を求めるものです。具体的には、家賃が6万円の物件であれば、契約終了後に退去が遅れた場合、毎月12万円を支払うことになります。
家賃滞納のみならず、契約違反等でも適用されます。消費者契約法上、問題ないかという点はこれまで裁判でも争われていますが、裁判所の判断としては、倍額程度であれば問題ない(有効)とするものが多いです。
実際、明渡義務があるのに従わない相手を追い出すためには、家主は相当の労力を強いられます。
弁護士費用もそうですし、訴訟、強制執行の実費も、時に数十万円になります。
そこで、高額の損害金の定めにより、相手に早期退去を促すことができますし、弁護士費用などの法的には請求が難しい費用についてカバーすることが可能です。
相手に資力がなければ回収が難しい場合もありますが、連帯保証人等からの回収の可能性もあります。こうした違約条項は、入れておくと、いざというときに非常に効果的です。
その他の条項
賃貸借契約書においては、上記の違約条項の他にも、是非、検討したいものとして、自動更新条項、緊急時の立入りの条項、解約予告期間の定め、合意管轄の条項、クリーニング費用の特約などがあり、必要に応じて内容を吟味することをお勧めします。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。
賃貸借契約の無催告解除特約
特約
賃貸借などの契約を締結する場合、その契約の一般的なルールとは異なる約束をすることがあります。そうした特別な約束を特約といい、契約書の最後に特約一覧の形でまとめる場合もありますし、契約書の関連箇所を修正したり、追加したりする場合もあります。
どのような約束をするかは基本的には自由ですので、双方の合意さえあれば、契約にどのような特約を付けてもかまいません。
しかし、契約の種類によっては、特約は何でもよいということではなく、一定の制限がかかっている場合があります。不動産賃貸借も、その特殊性から、特約には制限が課せられています。法律で明確に定められた制限もありますし、明文では規制がなくても、裁判例などから解釈上、制限されていると考えられるものもあります。
解除の原則(民法)
契約を解除方法は、法律で定められています。一般的なやり方は、民法541条の「催告による解除」というものです。
これは、相手が契約上の義務を履行しない場合に、「相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときに」解除ができるというものです。
不動産賃貸における家賃支払の場合で考えると、滞納が生じた後に「○月○日までに支払ってください」と伝えて、その期限が過ぎたら解除できるということです。一度は催告(催促)して支払のチャンスを与える必要があるということです。
無催告解除特約
無催告解除特約、と呼ばれる特約があります。これは読んで字のごとく、「催告なしで解除できるという特別な約束」です。
| 第○条 賃借人が、賃料の支払を2ヶ月分以上怠った場合、賃貸人は何等の通知催告を要せず、本契約を解除することができる。 |
民法では通常は催告をして相当期間(5日とか1週間とか)の経過後でなければ解除できませんが、その催告を要しないということです。
不動産賃貸の家賃支払義務をこれに当てはめると、家賃が遅れているときに、「契約は解除しました、出ていってください」とすることができるという特約です。本来なら必要な「家賃が遅れていますよ、○月○日までに必ず払ってくださいね」という催告が要らないということです。
不動産賃貸借における無催告解除特約の有効性
特約の有効性を考える場合、大きく3つがあります。①有効、②有効だが解釈上あるいは適用上の制限を受ける、③無効。
①有効な場合は、そのまま適用すればよいです。③無効な場合というのは、他の法令や公序良俗に反しているなどの理由で、その特約の効力を認めないので、特約がないことと同じです。
そして、不動産賃貸借における無催告特約は上記の②に当たります。
判例によると、「催告をしなくても不合理とは認められない事情がある場合」に限って無催告解除ができる特約、として有効とされています(最判S43.11.21民集22.12.2741)。
わかったようでわからない表現です。こうしたトートロジカルな表現を裁判所はよく使いますが、結局は経緯(滞納の金額や期間、その他の契約違反の有無、連絡状況など)を総合的に判断して、解除の有効性を決める、ということです。
結果的に、いざ裁判になった場合に解除の有効性が裁判所の判断に委ねられては困りますので、特約の存否に関わらず、催告が可能な場合は催告を行っておく、というのが現実的な対応となります。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。
賃貸借契約とは
不動産の賃貸借契約、名前を知らない人はほとんどいないと思いますが、あらためてどんな契約か、おさらいしてみます。
賃貸借契約
賃貸借契約は、有償で目的物を使わせる契約です。
典型的な契約は、基本的な法律である民法に載っています。誰でも身近に関わる、売買や雇用、請負などですが、賃貸借もそうした典型的な契約の一つです。
民法上、賃貸借契約は「当事者の一方がある物の使用収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する」ものです。
不動産の場合は、家主は「使用収益をさせる」義務があり、借主は「賃料(家賃)を支払う」義務と、最後に「返還する」義務があるのです。
民法と借地借家法
賃貸借契約は基本的で重要な契約ですので、上記の通り、民法に規定があります。しかし、民法の規定は不動産のみならず、様々な目的物の貸し借り(レンタル)に当てはまるものです。内容も様々な賃貸借の全てに当てはまるように定められています。
そこで、土地の(特に建物所有目的)賃貸借や、建物の賃貸借のために、定められている別の法律があり、それが借地借家法です。
借地借家法は賃貸借の中でも土地や建物の場合に特化していますので、民法にはない特別なルールも定められています。民法と借地借家法の内容が異なる場合は、より狭い範囲(不動産)にのみ適用される借地借家法が優先します。
借地借家法には、期間についての規定や、更新しない場合の「正当事由」の規定、一定の場合の借主に不利な契約内容の有効性、特殊な裁判手続、など、建物等の賃貸借契約にとって重要な規定が多く定められています。

その他の法律
建物の賃貸借をめぐっては、この他にも、消費者契約法やマンションの区分所有法、宅地建物取引業法などの他の法律も関係することがあり、それぞれの法律や関連法令を確認する必要があります。

東京都港区を拠点に、不動産賃貸に関する法律問題を数多く扱っている弁護士法人赤坂見附法律事務所です。家賃滞納や契約違反といったトラブルに、家主側の立場でスピーディかつ丁寧に対応しています。IT業界出身の経験を活かし、法律用語もわかりやすくご説明。オンラインでのご相談や全国対応も行っておりますので、どの地域からでもお気軽にご相談ください。